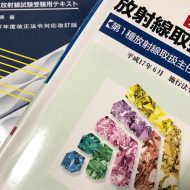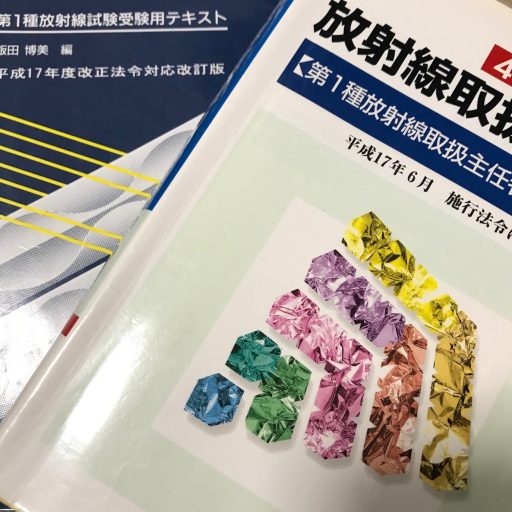胎児影響
母体が妊娠中に放射線被ばくを受けると、胎児も被ばくする可能性がある。これを体内被ばくという。胎児は母体内で絶えず成長・発達しており、放射線感受性が極めて高く、放射線防護の対象として重要である。放射線被ばくを受けた胎児の発達段階により、 胎児に現れる放射線影響の種類が異なることが大きな特徴である。これを胎児影響の時期特異性という。放射線影響の観点から胎児期は着床前期、器官形成期、胎児期の3つに区分される。
着床前期
卵管で受精した受精卵が子宮壁に着床するまでの時期で、受精後 8 日目までの期間である。この時期に受精卵が被ばくを受けた場合の影響は死亡(流産)である。しきい線量は 0.1 Gy である。被ばくを受けても死亡に至らなかったものは、成長を正常に続け 影響は何も残らないとされている。
器官形成期
器官形成期は細胞の分化が進み、器官・組織の基となる細胞が作られる時期で、着床後から受精 8 週までの時期である。この時期の影響は奇形の発生である。しきい線量は 0.15 Gy 程度と考えられている。
胎児期
器官形成期を過ぎ胎児期に入ると、胎児はヒトの形を呈し、盛んな細胞分裂により細胞数を増やし成長を続ける。受精 9 週から出生までが胎児期にあたる。受精 8 週 ~ 25 週の被ばくで精神発達遅滞が引き起こされる。受精 8 ~ 15 週の 感受性が高く、しきい線量は 0.2 ~ 0.4 Gy とされている。また、胎児期全体を通して発育遅延も影響としてあげられる。しきい線量は 0.5 ~ 1.0 Gy とされている。
胎児期の放射線影響
| 胎児期の区分 | 期間 | 発生する影響 | しきい線量(Gy) |
|---|---|---|---|
| 着床前期 | 受精 8 日まで | 胚死亡 | 0.1 |
| 器官形成期 | 受精 9 日 ~ 受精 8 週 | 奇形 | 0.15 |
| 胎児期 | 受精 8 週 ~ 受精 25 週 | 精神発達遅滞 | 0.2 ~ 0.4 |
| 受精 8 週 ~ 受精 40 週 | 発育遅延 | 0.5 ~ 1.0 | |
| 全期間 | – | 発がんと遺伝的影響 | – |
また下記のサイトに私がまとめた資料を示しております。