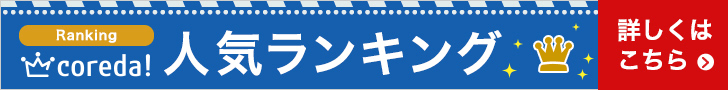相同組換え修復
相同組換え修復においては、その修復に、切断を受ける前に S 期で合成された姉妹染色分体の対応部位と相互に乗り換えることにより、正常な遺伝情報を鋳型として修復を行う。 この修復機構では、あたかも 2 組の 1 本鎖切断を修復することになるため、修復に間違いが起こることが少ない。修復には、切断端を DNA 組換えが可能なように整形するための DNA 消化酵素(ヌクレアーゼ)や、DNA のらせん構造を解くヘリカーゼといった酵素のほか、Rad52 などのタンパク質が必要とされる。
非相同末端結合
非相同末端結合は、切断部位をそのまま単純に再結合する修復機構で、DNA 依存性プロテインキナーゼ触媒サブユニット(DNA-Pkcs)や、Ku80、Ku70、XRCC4などのタンパク質が DNA の切断端に集まり修復に関与する。 理論的には非相同末端結合修復はいずれの細胞周期でも発現するが、G1 期や G0 期に活発に行われる。線維芽細胞では非相同末端結合修復をすると、細胞は損傷から回復することができず、 細胞生存率曲線は肩が小さくなり、より直線的に生存率が減少する。また正常線維芽細胞はよく増殖するため 5 Gy 程度で増殖死を起こす。
ヒトやマウスの細胞において、DNA2本鎖切断は主として、非相同末端結合と相同組換えの二つの機構で修復される。一般に、非相同末端結合は相同組換えに比べて誤りを起こしやすいと考えられている。 相同組換えによるDNA2本鎖切断の修復は鋳型として、姉妹染色分体を必要とするため、細胞周期のS期の後半からG2期に限定される。 この期間では、その他の期間と比べ放射線致死感受性は低い。またこの期間において非相同末端結合によるDNA2本鎖切断の修復機構は機能する。 非相同末端結合に関わるDNA依存性プロテインキナーゼ触媒サブユニット(DNA-PKcs)の遺伝子に変異を有する scid(スキッド)マウスは、放射線致死高感受性の他に免疫不全を呈する。 近年、ヒトでも DNA-PKcs の遺伝子に変異を有する患者が報告され免疫不全が認められている。
DNA損傷
Ⅰ
放射線により細胞には様々なタイプのDNA損傷が生じる。代表的なものとして、DNAで構成するチミンにヒドロキシラジカル(OH*)が付加されることで生じるチミングリコールなどの塩基損傷やDNA糖鎖の損傷によるDNA鎖切断がある。 塩基損傷の修復には塩基損傷の部位だけを切り出して正しい塩基を挿入する塩基除去修復と塩基損傷の周辺の塩基を含めた広い範囲を取り去り 修復を行うヌクレオチド除去修復がある。また、DNA鎖切断の一つであるDNA2本鎖切断の修復には非相同末端結合と相同組換えが関与する。この二つの修復には細胞周期に関連した 特徴があり、G1期の細胞では非相同末端結合による修復が主体となり、S期後半の細胞では相同組換えによるDNA2本鎖切断が効率的に修復される。
Ⅱ
放射線により細胞に生じたDNA損傷が正確に修復されないと細胞に突然変異が生じる可能性があり、がんや遺伝性影響リスクが増加すると考えられている。がんについては、放射線により白血病の発生リスクが増加することがよく知られている。原爆被爆者のこれまでの疫学調査の結果から、放射線による 白血病の過剰発生は被爆後約2年の潜伏期を経て、被爆後約7年前後にピークとなり、その後減少するという推移をたどる。この白血病の線量反応は、被ばく線量が2 Gy 以下では直線ー2次曲線 モデルに従う。また被ばく時年齢については、1 Gy 被ばくの場合の白血病死亡の過剰絶対リスクは10歳での被ばくは、30歳での被ばくと比較して高い。また病型別でみると、急骨髄性白血病発生の相対リスクは増加するか、慢性リンパ性白血病 のそれは有意な増加認められていないことが分かっている。また有意な増加が認められているのは、急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病である。
Ⅲ
生殖細胞の放射線被ばくにより子孫に現れる影響を遺伝性影響という。低LET放射線に関するマウスを用いた Rusell らの特定座位法による検討では、精原細胞の突然変異率は線量の増加とともに直線的に増加する。一方、同一線量で比較すると約 900 mGy/min の高線量率で 照射した場合は線量率が約 100分の1 である約 8mGy/min の場合と比べて突然変異率は高いことが分かっている。また、線量率が約 8mGy/min の場合と0.007 ~ 0.05 mGy/min の場合と比較すると、前者による突然変異率は後者と比べてほぼ等しい ことが示されている。放射線による生殖細胞の突然変異誘発率に関しては、生殖細胞の発育段階により差があり、精子は精原細胞より誘発率が高い。この要因の一つとして精子が精原細胞に比べて放射線による細胞致死感受性が低いことがあげられる。 放射線被ばくによる遺伝的影響うを評価する方法の一つに倍加線量法がある。倍加線量法では、自然発生する突然変異率と同率の突然変異を誘発する吸収線量を用いる。つまり、この吸収線量 が大きいほど子孫への影響は起こりにくいこととなる。
またこの他に放射線におけるDNA損傷には鎖切断・水素結合開裂・塩基損傷がある。
① 鎖切断:ポリヌクレオチド中のヌクレオチド間の結合切断による損傷
② 水素結合開裂:塩基間の水素結合のヌクレオチド間の結合切断による損傷
③ 塩基損傷:ヌクレオチドと塩基間の結合の切断や塩基への損傷
ヌクレオチドとはヌクレオシドにリン酸が結合した物質である。
Ⅳ
細胞の放射線致死感受性は、細胞が細胞周期のどの時期にあたるかのよって異なる。一般に細胞周期の G2 期から M 期にかけて放射線感受性は最も高く、 S 期後半で放射線感受性は最も低い。この細胞周期依存的な放射線感受性の違いは、放射線致死感受性を決定する最も重要な DNA 損傷である DNA 2 本鎖切断の修復能の違いによると考えられている。 DNA 2 本鎖切断は、非相同末端結合と相同組換え修復の主な2つの方法により修復されるが、相同組換え修復はより正確で間違えが少ない。 S 期後半では、 DNA 2 本鎖切断 が相同組換え修復により修復されるため放射線感受性が低いとされている。
補足
相同組換え修復は S 期後半から G2 期に誘導される DNA 2 本鎖切断の修復過程である。この修復では欠損した遺伝情報を相同な DNA と組換えて修復するため誤りが少ない修復機構となる。S 期後半には相同な 2 本 の DNA は合成されたばかりであり、両者の距離は近い。したがって、組換えも容易であり、修復の効率が良いことから、感受性は低くなる。一方、非相同末端結合は G1 期に 誘導される2本鎖切断の修復過程であり、組換えるべき相同な DNA は存在しないので、切断端を単に結合する修復過程をとることとなり、誤りがちな修復となる。
また下記のサイトに私がまとめた資料を示しております。
第1種放射線取扱主任者試験まとめ集