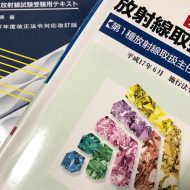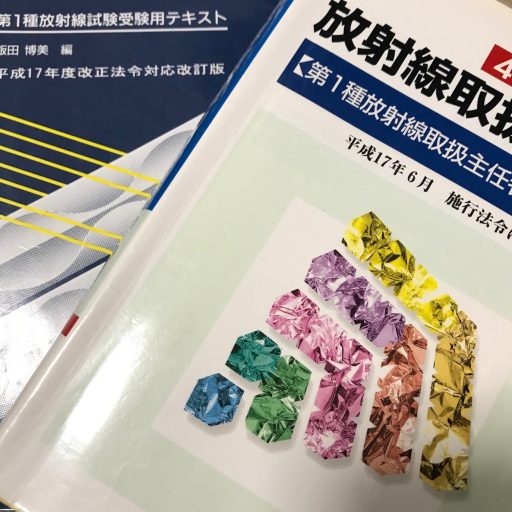突然変異
DNAの情報の変化の一つにDNAの酸化損傷による変異があげられる。ガンマ線による被ばく、太陽光による光励起された皮膚内色素、さらには体内の代謝過程で生成する活性酸素種など様々な要因でDNAは酸化される。これまでDNAを酸化する多くの系で、グアニンからチミンやシトシンへの突然変異が観察されてきた。このうちグアニン の酸化生成物である 8 – オキソグアニンはDNA複製においてアデニンを取り込むことが判明している。この性質がグアニンからチミンへの突然変異を引き起こすと提唱されている。紫外線により励起させた リボフラビンを用いて、DNA中において 8 – オキソグアニンとともにイミダゾロンが生成することが分かった。このイミダゾロンは生体内の条件で徐々に加水分解を受け、オキサゾロンが生成する。 オキサゾロンに対する塩基取り込みを解析したところ真核生物DNAポリメラーゼα、β、εはオキサゾロンに対してグアニンを優先的に取り込んだ。特にポリメラーゼαとεについては、DNA複製の中心的役割うぃ担う酵素であり、かつDNAポリメラーゼεの 構成機構をスルーしてグアニンを取り込み、オキサゾロンを乗り越えてさらに伸長されてしまうことはオキサゾロンがグアニンからシトシンを引き起こすDNA損傷であるといえる。
遺伝子突然変異
遺伝子本体は DNA であり、DNA 損傷などにより遺伝情報が変化することを遺伝子突然変異という。この場合、遺伝子だけが変化しており、染色体の構造に変化は見られない。 点としての遺伝子が変化するということから点突然変異とも呼ばれる。
染色体突然変異
染色体突然変異では、染色体の構造に変化が生じ、その変化に伴い染色体上の遺伝子に変化が生じる。染色体突然変異は遺伝子側に注目した呼び方であるが、染色体側に注目した呼び方は染色体異常である。 染色体異常の原因は染色体の切断であり、切断の大部分は修復されるが、切断されたままであったり、誤って再結合した場合に異常が現れる。染色体異常の型には欠失、逆位、環状染色体、転座、2動原体染色体 などがある。
① 欠失・・・同一腕内の 2 ヶ所に切断が起こり中央部が欠失した腕内欠失と 1 ヶ所で切断が起こり末端部が欠失した末端欠失がある。
② 逆位・・・2 ヶ所で切断が起こり、中央部が 180°回転して再結合したもの。
③ 環状染色体・・・両腕で切断が生じ、動原体を含む中央部の両端が再結合しリング状になったもので、リングとも呼ばれる。
④ 転座・・・2 個の染色体の間で部分的に交換が起こったもの。
⑤ 2動原体染色体・・・転座の交換の仕方によっては動原体を持った2動原体染色体が生じる。主に G1 期の被ばくによりなり、G2 期の時に染色分体異常が起きる。
環状染色体や 2動原体染色体は細胞分裂に際してうまく両極に分かれることがでず、異常は比較的早期に消失する。これを不安定型の異常という。一方、欠失、逆位、転座などは 細胞分裂によっても引き継がれ長期にわたって存在し、安定型の異常(発がんしやすい異常)といわれる。放射線の生物影響に基づき被ばく線量を推定する方法をバイオドシメトリ (生物学的線量算定)と呼ぶ。染色体異常の発生は確率的であり、低線量域では統計的なバラツキが大きい。染色体異常は染色体型と染色分体型に分けられる。 DNA 合成期より前(G1期での照射)に染色体が切断される(1対の染色分体の同じ位置に異常が認められる)と M 期で染色体型、DNA 合成期より後(G2期での照射)に染色体分体が切断されると M 期で染色分体型の異常となる。
ベルゴニー・トリボンドーの法則
ベルゴニーとトリボンドーは「放射線感受性は細胞分裂の頻度の高いものほど、将来行う細胞分裂の数が多いものほど、形態・機能が未分化なものほど高い」という 3 点からなる放射線感受性についてのベルゴニー・トリボンドーの法則をまとめた。 成人において細胞分裂の頻度が高いのは細胞再生系であり、造血臓器(骨髄)、小腸、皮膚、水晶体、精巣(睾丸)などがこれに属する。さらに、細胞再生系には芽球(骨髄)や精原細胞(精巣)といった未分化な細胞も存在し、放射線感受性は高い。また、小児 あるいは胎児は活発な成長・発達をしており、将来行う細胞分裂の数も多く、細胞再生系に限らず全体の放射線感受性が高い。
また下記のサイトに私がまとめた資料を示しております。