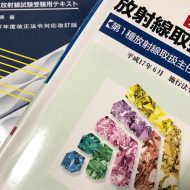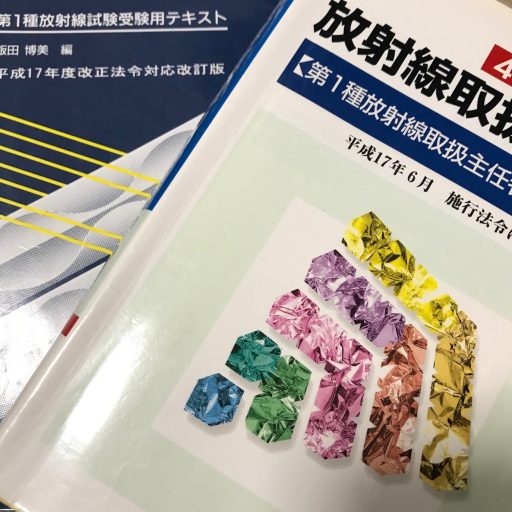内部被ばくに関する記述
Ⅰ
放射性物質が体内に侵入経路には経口摂取、吸入摂取、経皮侵入の3つの経路がある。経口摂取された放射性物質の消化管吸収率は、ヨウ素のように高いものと酸化プルトニウムのように 低いものものとがあり、吸収率は放射性物質の種類により異なる。血液中に入った放射性物質は、その化学的性質に従って特有の分布をする。トリチウムやセシウムは全身にほぼ均等に 沈着し、カルシウムやストロンチウムは骨に、ヨウ素は甲状腺に沈着する。組織に沈着した放射性物質の多くは、主に尿、糞により体外に排出される。排出速度は生物学的半減期により表され 被ばく線量率は物理的半減期と生物学的半減期から計算される実効半減期に従って減少する。実効半減期は、式(生物学的半減期×物理学的半減期)/(生物学的半減期+物理学的半減期)により計算される。吸入により放射性物質を取り込んだ場合にも 体内移行率の高い放射性物質であれば経口摂取とほぼ同様な挙動を取るが、酸化プルトニウムのように体液に溶解しにくいものでは肺やそのリンパ節に長期間渧留する。
Ⅱ
放射性物質の摂取による体内被ばく線量を評価するためにの主な方法としては、生体試料を用いるバイオアッセイと全身に沈着した放射性物質から放出される γ 線を体外から 全身カウンタを用いて検出する方法とがある。この他に、特定の器官に着目して、その器官に沈着している放射能の測定を目的とした甲状腺モニタなどがある。バイオアッセイの試料としては主に 尿、糞が用いられるが、必要に応じて血液なども用いられる。事故時のように吸入摂取が疑われる場合には、鼻スミア試料を採取することが重要である。放射性物質の 体内量は、測定された試料中の放射能を、摂取した核種の人体における代謝モデルに当てはめることにより求められる。体内量は国際放射線防護委員会(ICRP)による排出率関数 などで計算される。精密型全身カウンタは、バックグラウンド放射線による計算を少なくするための遮蔽室と検出器及び放射線計測部(データ解析部)からなっている。検出器としては一般にNaI(Tl)シンチレーションカウンタが用い られてきたが、近年ではエネルギー分解能が優れたGe検出器が用いられるようになっている。
Ⅲ
体内汚染がわかった場合には放射性物質の体外除去が行われる。胃腸管からの吸収低減のためには、胃腸管の洗浄、下剤の投与、プルシアンブルーなどのイオン交換剤の投与等 が行われる。体内に吸収された放射性物質を除去するための処置としては、① ヨウ化カリウムなどの安定同位体を含む化合物の投与、② DTPAなどのキレート剤の投与、③ 利尿剤の投与 などが考えられる。どの方法を選択するかは、放射性物質の性質による。
また下記のサイトに私がまとめた資料を示しております。