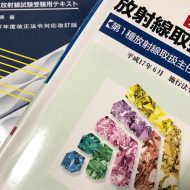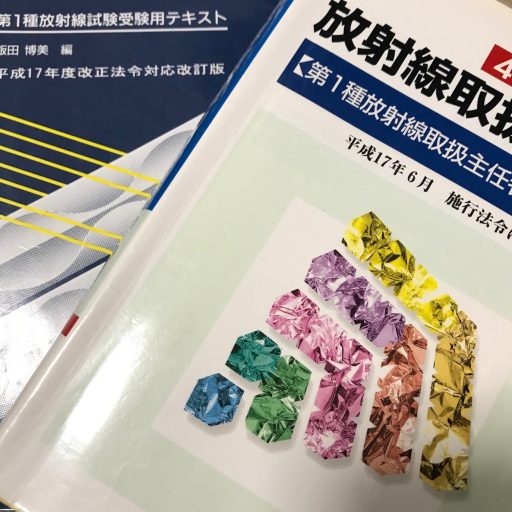分裂遅延
細胞は放射線照射されると、分裂頻度の低下や細胞周期の延長が見られ、分裂が遅延する。細胞周期のうち G2 期に留まることにより分裂遅延は起こっており、G2 ブロックと呼ばれる。
細胞死(分裂死と間期死)
細胞がある程度の放射線照射を受けると細胞死を起こす。照射された細胞では分裂停止はするが、代謝は継続されて巨細胞がみられる。細胞死は細胞周期の観点から分裂死と間期死に、細胞死の形態の観点からネクローシスとアポトーシスにそれぞれ分類される。
分裂死
分裂死は増殖死とも言われ、活発に細胞分裂している細胞が放射線照射を受けた後に数回の分裂を経てから死に至るものである。細胞分裂を停止しても DNA やタンパク質の合成は続けられており、このため巨細胞が形成されたり、 隣接した細胞同士で核の融合が起こることがある。分裂死は、骨髄や腸の幹細胞、腫瘍細胞、培養細胞など盛んに分裂している細胞で見られる。
間期死
間期死は、間期にある細胞が放射線照射を受けた後、分裂することなく死に至るものである。もはや細胞分裂を行わない神経細胞、筋細胞などの分化した細胞で間期死は見られ、 細胞分裂している細胞でも分裂死が起こる線量よりもさらに大きな線量が与えられると間期死が起こる。これらを低感受性間期死という。一方、リンパ球や卵母細胞などでは低線量の照射で間期死が見られ、これを高感受性間期死 として区別している。
ネクローシスとアポトーシス
ネクローシスは従来から考えられていた病理的で受動的な死である。一方、アポトーシスは生理的で能動的な死であり、損傷を受けた細胞が積極的に自己を排除するために起こると間会えられている。 このため、プログラム死と呼ばれることもある。リンパ球などで見られる高感受性間期死はアポトーシスである。
ネクローシスの形態学的変化
傷害を受けた細胞の受動的・病理的死で細胞の膨化・ミトコンドリアの変化が起こる。
アポトーシスの形態学的変化
能動的・生理的な細胞死で細胞の縮小・核濃縮・核の断片化・核内のクロマチンの凝縮・細胞の分断化・アポトーシス小体の形成。この他にもミトコンドリアの形態的変化、数の減少・紡錘体の大きさの減少・中心体の増加、マクロファージによる貪食などがある。
オートファジー(自己融解死)
細胞内で過剰にタンパク質が作られたり、異常となった場合に小胞を作り分解することをいい、この時に作られる小胞をオートファジー小胞、オートファゴソームという。
放射線による細胞死に関する記述
Ⅰ
放射線による細胞死には様々な様式が存在する。主なものとしては、細胞が大きくなり細胞内容が流出することが特徴的な細胞死である壊死(ネクローシス)と、細胞が小さくなり核が凝縮するアポトーシスがあげられる。これらの細胞死では細胞死に伴い DNA は断片化されるが、断片化の形式は細胞死により異なる。壊死(ネクローシス)では断片化された DNA は電気泳動により観察するとスメア状となるが、アポトーシスでは 梯子状(はしご)となる。放射線生物学においては放射線照射後の細胞生存率を定量する場合に、上に述べたような一般的な細胞死の他に細胞増殖能を喪失を “細胞死” として取り扱う。この様式の “細胞死” としては、代謝を保ちながら細胞の分裂が不可逆的に停止し細胞増殖能を形成する老化(セネッセンス)があげられる。
補足
DNA 損傷等の障害が何もなくとも、細胞が分裂できる回数には限界があることが知られており、限界に達して細胞分裂を失った状態はセネッセンス(細胞老化)と呼ばれる。
Ⅱ
Ⅰ で述べた放射線生物学における細胞死の概念を踏まえ、放射線照射後の細胞生存率を定量する手法としてコロニー形成法が一般に用いられる。コロニー形成法では、細胞を単一細胞に分離して細胞培養皿に播種し、一定期間培養した後に生じるコロニー数を計数する。通常、細胞を播種した後 7 ~ 21 日程度してから 50 個以上の細胞からなるコロニー数を計数する。計数したコロニー数を播種した 細胞数で除した値をコロニー形成率という。放射線照射後の細胞生存率は、放射線を照射した細胞のコロニー形成率を、照射してない細胞のコロニー形成率で除した割合で表す。コロニー形成法により得られた細胞生存率から細胞生存率曲線を描くが、通常、細胞生存率曲線は縦軸に生存率を対数目盛で示し、横軸に吸収線量を線形目盛で示す。
解説
分裂する細胞の細胞生存率の定量には、コロニー形成法を用いる。50 個程度以上の細胞からなる肉眼で観察可能なコロニーを計数する。コロニー形成率は、非照射(コントロール群)においても播いた細胞がすべてコロニーを作る訳ではないので、照射群と非照射群のコロニー形成率の比から求める。。
Ⅲ
放射線照射後の細胞生存率は、照射条件あるいは培養条件によって変化する。培養細胞に低 LET 放射線を照射した場合、総吸収線量が同一であるならば 1 回で照射したときと比較して、2 回に分けて時間間隔をおいて照射したときに細胞生存率は高くなる。この現象は亜致死損傷回復によると考えられている。低 LET 放射線では、特別な場合を除けば吸収線量が同じであれば線量率が低くなると生物効果は小さくなる。また、培養細胞に 低 LET 放射線を照射した後の培養条件によって細胞の生存率の上昇が見られることがある。これは潜在的致死損傷回復によると考えられている。
補足
亜致死損傷(SLD)回復は、標的説に基づき定義され、線量率効果の機構の説明に用いられる。また、潜在的致死損傷(PLD)回復は、プラトー期や低栄養などの細胞の生育条件が悪い時に見られる減少として知られている。
また下記のサイトに私がまとめた資料を示しております。