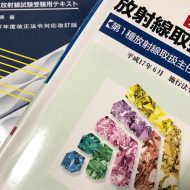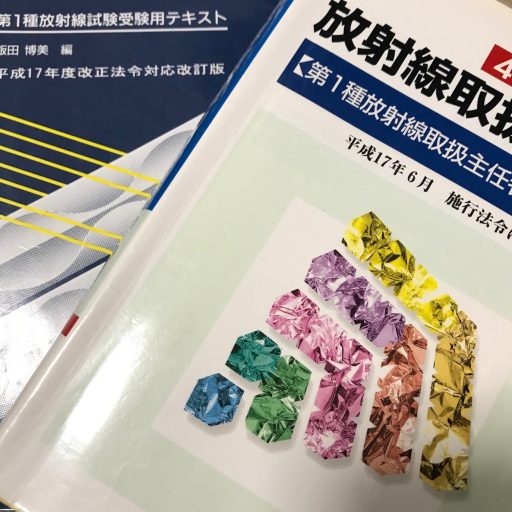実効線量の評価についての記述
Ⅰ
低線量放射線の確定的影響)を評価するための線量として実効線量が定義されている。実効線量は線質効果と組織の感受性を勘案して評価されるが、直接測定することができないため 測定できる実用的な「測定量」と次のように関連付けられている。外部被ばくに関連する測定量には、70μm線量当量、3mm線量当量及び1cm線量当量がある。放射線防護上重要な細胞が 表面からどれほどの深さに存在するかに応じて適用される。 3mm 線量当量は眼の水晶体の等価線量に対応し、、 70μm 線量当量は皮膚の等価線量に対応する。全身均等被ばくの場合 には、所定の場所に装着された個人被ばく線量計により測定された 1cm 線量当量の値を実効線量とする。不均等被ばくの場合には、次式にしたがって算出する。
実効線量 H = 0.08Ha + 0.44Hb + 0.45Hc + 0.03Hm
Ha : 頭部及び頸部における 1cm 線量当量
Hb : 胸部及び上腕部における 1cm 線量当量
Hc : 腹部及び大腿部における 1cm 線量当量
Hm : 上の各部分のうち線量当量が最大となるおそれのある部分における 1cm 線量当量である。
例えば、頭頸部のみに5.0mSvの被ばくがあったとすると、実効線量は 0.55 mSvと算定される。
Ⅱ
体内に取り込まれた放射性物質は、減衰し排泄されつつ長期間にわたって周囲の組織に線量を与え続ける。摂取時から50年間(成人の場合)にわたって積分した線量に、 放射線の線質を考慮した放射線荷重係数を乗じて得られる線量を預託等価線量と呼ぶ。これに組織・臓器ごとに定められている組織荷重係数を乗じた上で足し合わせて預託実効線量が定義される。 内部被ばくに伴う実効線量とはこれを指す。組織荷重係数を表1に示す。
表1
| 組織・臓器 | 組織荷重係数 |
|---|---|
| 生殖腺 | 0.20 |
| 赤色骨髄・結腸・肺・胃 | 0.12 |
| 膀胱・乳房・肝臓・食道・甲状腺 | 0.05 |
| 皮膚・骨表面 | 0.01 |
| 残りの組織・臓器 | 0.05 |
| 合計 | 1.0 |
125Iを吸入した場合、その大部分は甲状腺に分布する。125Iが放出するγ線やX線の放射線荷重係数は 1 なので、甲状腺の預託等価線量が10mSvの時の実効線量は 0.5 mSvとなる。 また、空気中のラドン及びその娘核種の吸入による被ばくが最も大きな組織は肺である。ラドン及びその娘核種の壊変に伴って放出されるα線の放射線荷重係数は 20 なので、 吸入されたラドン及びその娘核種による実効線量が1.2mSvと算定されたときの肺の等価線量は 10 mSv、吸収線量は 0.5 mSvである。
Ⅲ
核種と化学形ごとに摂取された単位放射能当たりの実効線量が計算されている。この換算係数を実効線量係数と呼ぶ。3Hに関する実効線量係数を表2に示す。
表2
| 核種 | 化学形等 | 吸入摂取した場合の実効線量係数[mSv/Bq] |
|---|---|---|
| 3H | 元素状水素 | 1.8 × 10^(-12) |
| 3H | メタン | 1.8 × 10^(-10) |
| 3H | 水 | 1.8 × 10^(-8) |
| 3H | 有機物(メタンを除く) | 4.1 × 10^(-8) |
| 3H | 上記を除く化合物 | 2.8 × 10^(-8) |
これを用いれば、トリチウム水蒸気4.9 × 10^6を吸入摂取した場合の実効線量は 8.8 × 10^(-2) mSvと評価できる。
解説
水蒸気なので、表2の水の欄の値を用いる。 1.8 × 10^(-8) × 4.9 × 10^6 = 8.8 × 10^(-2) mSv
また下記のサイトに私がまとめた資料を示しております。