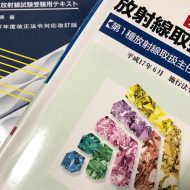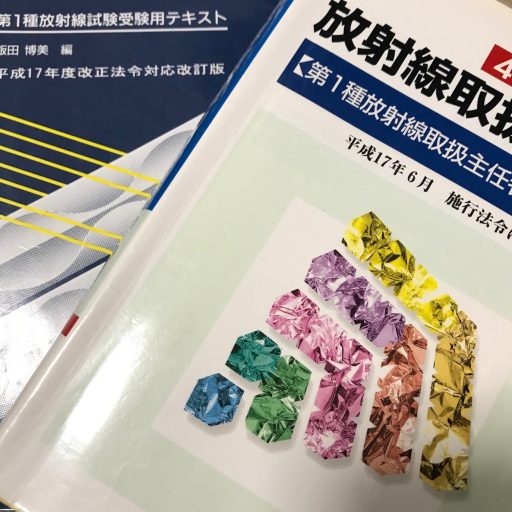DNA損傷
放射線により細胞には様々なタイプのDNA損傷が生じる。代表的なものとして、DNAで構成するチミンにヒドロキシラジカル(OH*)が付加されることで生じるチミングリコールなどの塩基損傷やDNA糖鎖の損傷によるDNA鎖切断がある。 塩基損傷の修復には塩基損傷の部位だけを切り出して正しい塩基を挿入する塩基除去修復と塩基損傷の周辺の塩基を含めた広い範囲を取り去り 修復を行うヌクレオチド除去修復がある。また、DNA鎖切断の一つであるDNA2本鎖切断の修復には非相同末端結合と相同組換えが関与する。この二つの修復には細胞周期に関連した 特徴があり、G1期の細胞では非相同末端結合による修復が主体となり、S期後半の細胞では相同組換えによるDNA2本鎖切断が効率的に修復される。
放射線により細胞に生じたDNA損傷が正確に修復されないと細胞に突然変異が生じる可能性があり、がんや遺伝性影響リスクが増加すると考えられている。がんについては、放射線により白血病の発生リスクが増加することがよく知られている。原爆被爆者のこれまでの疫学調査の結果から、放射線による 白血病の過剰発生は被爆後約2年の潜伏期を経て、被爆後約7年前後にピークとなり、その後減少するという推移をたどる。この白血病の線量反応は、被ばく線量が2 Gy 以下では直線ー2次曲線 モデルに従う。また被ばく時年齢については、1 Gy 被ばくの場合の白血病死亡の過剰絶対リスクは10歳での被ばくは、30歳での被ばくと比較して高い。また病型別でみると、急骨髄性白血病発生の相対リスクは増加するか、慢性リンパ性白血病 のそれは有意な増加認められていないことが分かっている。また有意な増加が認められているのは、急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病である。
生殖細胞の放射線被ばくにより子孫に現れる影響を遺伝性影響という。低LET放射線に関するマウスを用いた Rusell らの特定座位法による検討では、精原細胞の突然変異率は線量の増加とともに直線的に増加する。一方、同一線量で比較すると約 900 mGy/min の高線量率で 照射した場合は線量率が約 100分の1 である約 8mGy/min の場合と比べて突然変異率は高いことが分かっている。また、線量率が約 8mGy/min の場合と0.007 ~ 0.05 mGy/min の場合と比較すると、前者による突然変異率は後者と比べてほぼ等しい ことが示されている。放射線による生殖細胞の突然変異誘発率に関しては、生殖細胞の発育段階により差があり、精子は精原細胞より誘発率が高い。この要因の一つとして精子が精原細胞に比べて放射線による細胞致死感受性が低いことがあげられる。 放射線被ばくによる遺伝的影響うを評価する方法の一つに倍加線量法がある。倍加線量法では、自然発生する突然変異率と同率の突然変異を誘発する吸収線量を用いる。つまり、この吸収線量 が大きいほど子孫への影響は起こりにくいこととなる。
またこの他に放射線におけるDNA損傷には鎖切断・水素結合開裂・塩基損傷がある。
① 鎖切断:ポリヌクレオチド中のヌクレオチド間の結合切断による損傷
② 水素結合開裂:塩基間の水素結合のヌクレオチド間の結合切断による損傷
③ 塩基損傷:ヌクレオチドと塩基間の結合の切断や塩基への損傷
ヌクレオチドとはヌクレオシドにリン酸が結合した物質である。
また下記のサイトに私がまとめた資料を示しております。