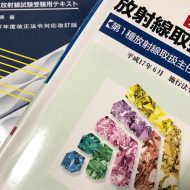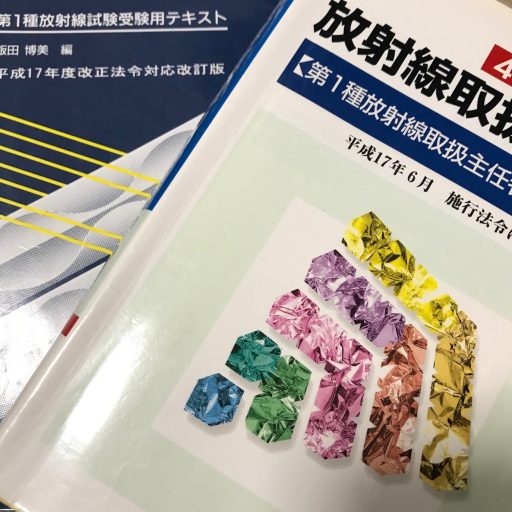発がん
発がんの最低潜伏期間は白血病で 2 年、その他の固形がんで 10 年とされており、晩発影響に区分される。
確率的影響としての遺伝的影響
遺伝的影響は、生殖細胞が放射線被ばくすることにより遺伝子突然変異や染色体異常が引き起こされ、それが子孫に引き継がれて発生する。原爆被ばく者の疫学調査などのヒトに関するデータからは 遺伝的影響の優位な増加は認められていない。しかし、動物実験などから放射線被ばくにより遺伝的影響が生じることが確かめられているので、発がんとともに確率的影響に区分し放射線防護の対象としている。
遺伝的影響の発生確率の推定(直接法)
突然変異率から遺伝的影響の発生率を直接推定する方法で、突然変異率を動物実験により求め、線量率効果、動物種差、1形質から全優性遺伝への換算、表現型の重篤度などの要因により補正・外挿し、遺伝的影響の発生率を算定する。
遺伝的影響の発生確率の推定(間接法)
自然発生の突然変異率を 2 倍にするのに必要な線量を倍加線量というが、ヒトの遺伝的疾患の自然発生率と動物実験による倍加線量を比較して推定する方法をいう。倍加線量として 1 Gy の値が示されている。(ヒトの場合0.2 ~ 2.5 Gy と幅がある。)
倍加線量
① 倍加線量は自然発生と同じだけの影響を起こすのに必要な線量であり、倍加線量が大きいということは、一定の影響を起こすために大きな線量が必要であるということを示すので、感受性が低いことを意味する。したがって、倍加線量が大きいほど遺伝的影響は起こりにくいということを意味する。
② 倍加線量の逆数は単位線量あたりの相対突然変異リスクを表す。
③ 誘発突然変異率 = 自然突然変異率 × (被ばく線量/倍加線量)。線量率を下げれば突然変異率は減少する。また点突然変異は1箇所の変化に基づくため線量に比例する。
放射線被ばくによる急性障害と晩発影響についての記述
Ⅰ
高線量放射線を一度に全身被ばくしたような場合、数週間以内に現れる障害を急性障害という。占領によって症状は異なるが、典型的な経過は以下の 4 つの病期に分けられる。被ばく直後から数時間以内に悪心、嘔吐、発熱など非特異的な症状が現れる前駆期、これらの症状が一時的に消失する潜伏期、骨髄や消化管障害、脱水など多彩な症状が現れる発症期、その後回復期あるいは死亡の 4 期である。障害の現れ方やその時期は、線量及び臓器・組織によって異なる。例えば、ヒトが高線量のγ線を全身被ばくしても医療処置がなされないと、3 ~ 10 Gy では 3 ~ 4 週間程度で骨髄の障害により、10 ~ 20 Gy では、1 ~ 2 週間程度で腸管の障害により死亡する危険性が高い。
解説
Ⅰ は急性放射線症についての出題である。前駆期は被ばく後 48 時間以内を指し、悪心、嘔吐、下痢、発熱、頭痛、意識障害等の症状が現れる。唾液腺の腫脹、圧痛および口腔粘膜の毛細血管拡張などが診察時の留意点と言われている。
Ⅱ
臓器や組織の急性障害は、主に臓器・組織の実質細胞の死によって起こると考えられる。臓器や組織によって実質細胞の放射線感受性が違うために、障害を認めるようになるしきい線量も臓器や組織によって異なる。一般に、現れる障害の重篤度は、被ばくした線量が大きいと高い。1 回のγ線による被ばくでは、抹消血中のリンパ球数の減少は 0.5 Gy 以上の被ばくによって起こる。女性の永久不妊は 6 Gy 以上の生殖腺被ばくによって起こり、男性の永久不妊は 6 Gy 以上の生殖腺被ばくによって起こる。又、男性の一時的不妊のしきい線量は 0.15 Gy で、女性の一時的不妊が起こる線量は男性に比べて高い。
Ⅲ
晩発影響としては、発がん、白内障、遺伝的影響などが挙げられる。発がんと遺伝的影響は、確率的影響と考えられている。一般に、被ばくしてから発がんまでの期間は固形がんでは白血病に比べて長い。白内障は確定的影響に分類され、水晶体の混濁による。遺伝的影響は放射線に被ばくした生殖細胞に遺伝子の突然変異や染色体異常が起こることによる。遺伝的影響のリスクの推定には倍加線量法と、線量効果関係を動物実験によって求め、 これをヒトに適用して行う直接法とがある。遺伝的影響のリスクは、倍加線量が大きいほど低く、一般的に線量率が低いほど低い。UNSCEAR(原子放射線の影響に関する国連科学委員会) 2001 年報告では倍加線量を 1 Gy と見積もっている。
また下記のサイトに私がまとめた資料を示しております。