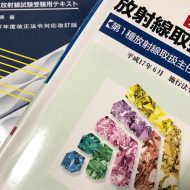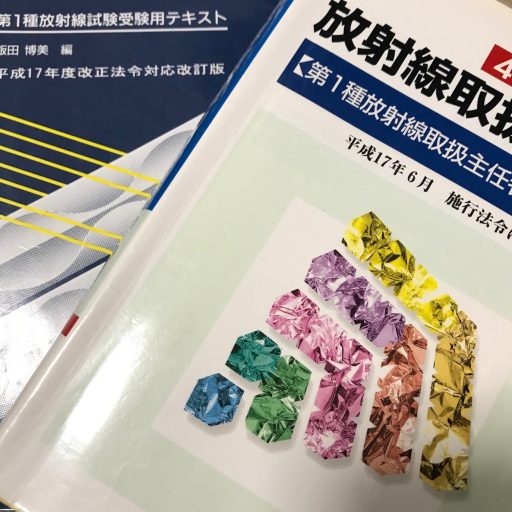臓器・組織の放射線感受性
細胞や臓器・組織の種類によって放射線感受性はっよて決まる。一般に、臓器・組織の放射線感受性は、その臓器・組織を構成している細胞の放射線感受性によって決まる。臓器・組織を成人における放射線感受性によって 大まかに分類すると下の表の通りとなる。
| 感受性の程度 | 組織 |
|---|---|
| 最も高い | リンパ組織(胸腺、脾臓)、骨髄、生殖腺(精巣、卵巣) |
| 高い | 小腸、皮膚、毛細血管、水晶体 |
| 中程度 | 肝臓、唾液腺 |
| 低い | 甲状腺(45Gyで機能を失う)、筋肉、結合組織 |
| 最も低い | 脳、骨、神経組織 |
臓器・組織の確定的影響
造血臓器は、赤血球、白血球などの血液細胞(血球)を産生する臓器であり、骨髄、リンパ球がこれにあたる。胎児期には、肝臓、脾臓も造血機能を持つ。骨髄は造血機能を持つ赤色骨髄と脂肪変性して造血機能を失った 白色骨髄(黄色骨髄)に分けられる。小児期において、ほとんど全ての骨髄が赤色骨髄であるが、年齢が増大すると白色骨髄の割合が大きくなる。赤色骨髄が 0.5 Gy 程度被ばくすると、造血機能の低下が起こり 血球の供給が止まる。このため、造血臓器の放射線障害は末梢血中の血球数の変化によって検出できる。しかし一方では、放射線被ばくによりリンパ球は血球自体の細胞死が引き起こされるし、他の血球においても 寿命が尽きたものは死んで抹消血中から除かれていく。したがって、放射線影響による血球数の変化は、造血臓器と抹消血球の両方について供給と減少の関係を総合してとらえることが重要である。赤血球および血小板は核を持たないが、 白血球には核がある。白血球は起源や形態から、リンパ球と顆粒球に分類され、さらに顆粒球は、酸性や塩基性の染色液によく染まるか否かおよび形態の観点から、好酸球、好中球、好塩基球および単球に分類される。白血球においては、 リンパ球を除き、顆粒球の種類による放射線影響の違いは特にない
白血球
白血球は免疫応答、貪食作用などの機能を持つ。したがって、白血球の減少により、免疫機能の低下が起こり細菌観戦への抵抗性が減少する。
リンパ球(間期死)
リンパ芽球、幼若リンパ球、リンパ球と分化するが、分化しても放射線感受性は低下せず、抹消血中の成熟リンパ球の放射線感受性までも高いことが特徴である。放射線被ばくにより抹消血中のリンパ球は細胞死を起こすため、供給の低下を 待たずに被ばく直後(24時間で出現)からリンパ球は減少する。リンパ球減少のしきい線量は 0.25 Gy である。リンパ球の回復は他の血球に比べて遅い。
B細胞・・・B細胞はリンパ球の中で最も感受性が高い。骨髄由来。
T細胞・・・T細胞は胸腺由来のリンパ球。
NK細胞・・・NK細胞はリンパ球の1つ。細胞性免疫、液性免疫の過程を経ず、NK細胞はウイルス等の異物を攻撃する。このため、Natural Killer 細胞と呼ばれる。
形質細胞・・・B細胞が分化した細胞で、免疫グロブリンを産生する。感受性は低くなる。
マクロファージ・・・単球の成熟過程から派生する貪食細胞。感受性は他の白血球と同程度。
顆粒球
骨髄芽球の放射線感受性が最も高く、分化の進行に伴って次第に低下し、成熟抹消顆粒球の放射線感受性が最も低い。顆粒球の減少はリンパ球にやや遅れて始まり、被ばく後 3 ~ 4 日後で最低値を示す。被ばく直後に 一過性の顆粒球数の増加が見られることがあるが、これは脾臓などの貯蔵プールから一過性の放出が行われるため起こると考えており、初期白血球増加と呼ばれる。
血小板
赤血球は寿命が 60 ~ 120 日と長いため供給の低下の影響が現れにくく、血球数の変化は他の血球に比べてそれほど顕著ではない。
生殖腺(精巣)・・・線量率効果がない
男性の生殖腺は精巣(睾丸)であり、精原細胞 → 精母細胞 → 精子細胞 → 精子と約 70 日かけて分化・成熟する。放射線感受性は後期精原細胞が最も高く、0.15 Gy の急性被ばくにより細胞死が起こり、一過性の不妊が生じる。 この 0.15 Gy という線量は急性被ばくのしきい線量としてはかなり低いものであるが、分割照射や低線量率被ばくの場合でもしきい線量はそれほど変わらず、線量率効果がないことに注意が必要である。3.5 ~ 6 Gy を越える 線量では幹細胞(精原細胞)はほとんど死んでしまい、永久不妊が起こる。長時間での被ばくでの一時的不妊の線量率のしきい値は約 0.4 Gy/年で推定できる。また突然変異感受性は、精細胞 > 精母細胞 = 精子 > 精原細胞 である。
生殖腺(卵巣)
女性の生殖腺は卵巣であり、卵原細胞 → 卵母細胞 → 卵子 と分化・成熟する。胎児期にすでに卵母細胞(未成熟)までの分化が進んでおり、その段階で停止している。思春期を迎えると卵母細胞以降の分化が再開され月経の度に 排卵される。静止期にある卵母細胞の放射線感受性は比較的低いが、分化が再開された卵母細胞の放射線感受性は非常に高く、高感受性間期死の形を取り細胞死を起こす。 0.65 Gy ~ 1.5 Gy で一過性の不妊が生じる。 2.5 ~ 6 Gy で卵巣に蓄えられている未成熟卵母細胞が死滅し永久不妊となる。永久不妊のしきい線量は、若年層で高く年齢の増加に伴い低くなる傾向が見られる。
小腸
小腸の粘膜には絨毛があり、その付け根にはクリプト(腺窩)と呼ばれる分裂を盛んに行なっている細胞がある。クリプトから分化する細胞は吸収上皮細胞であり、順次先端方向へ押し上げられていき、先端部で先端部で寿命を全うし脱落していく。 小腸が 10 Gy 以上の急性照射を受けた場合、クリプトの細胞分裂が停止し、吸収上皮細胞の供給が絶たれ、粘膜上皮の剥離、萎縮および潰瘍が発生し、脱水症状も現れる。
皮膚
皮膚は表面から表皮、真皮、皮下組織の順に配列している。表皮の最下層は基底細胞膜といわれ、細胞分裂を盛んに行なっており放射線感受性の高い部分である。基底細胞層は波打っており、平均 70 μm の深さにある。 法令で個人被ばく線量測定が義務付けられている 70 マイクロメートル線量当量は、この基底細胞層の深さに対応している。分裂した細胞は表面方向に押し上げられ、順次角質化し脱落している基底細胞の被ばくは、皮膚紅斑 や落屑の原因となる。また、毛のうは真皮内にあり、細胞分裂を盛んに行い、毛の伸長のもととなっている。毛のうの放射線感受性は高く、放射線被ばくは脱毛の原因となる。下の表に皮膚の影響としきい線量 を示す。被ばく線量が増すと、潜伏期が短くなり、症状の重篤度が増す。
皮膚の放射線影響としきい線量
| 線量 | 放射線影響 |
|---|---|
| 3 Gy 以上 | 脱毛 |
| 3 ~ 6 Gy | 紅斑・色素沈着 |
| 7 ~ 8 Gy | 水泡形成 |
| 10 Gy 以上 | 潰瘍形成 |
| 20 Gy 以上 | 難治性潰瘍(慢性化、皮膚がんへの移行) |
水晶体
水晶体前面の上皮細胞は放射線感受性が高く、放射線被ばくにより損傷を受けると水晶体混濁の原因となる。水晶体混濁の程度が進んで視力障害が認められるような状態になったものを白内障という。 水晶体の前方には 3 mm の角膜が存在するが、法令で個人被ばく線量の評価が義務付けられている 3 ミリメートル線量当量はこの暑さに対応している。1 回照射の場合のしきい線量は 水晶体混濁で 2 Gy 、白内障で 5 Gy 、慢性被ばくの場合では水晶体混濁が 5 Gy 、白内障で 8 Gyとされている。水晶体は何年にもわたる被ばくでの線量率しきい値は 0.15 Gy/年をいくぶん上回る程度で白内障がでると推定されている。
また下記のサイトに私がまとめた資料を示しております。